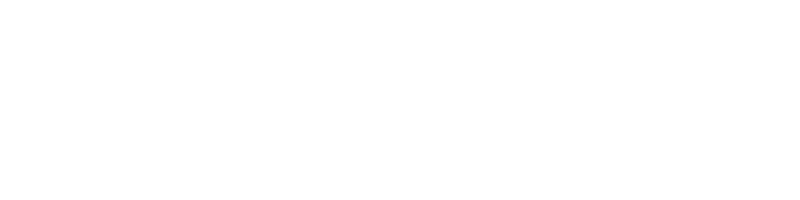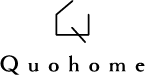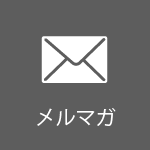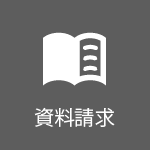家づくりのお金が全部わかるコラム
1-1 家づくりにかかるお金の基礎知識
家づくりにはさまざまなお金がかかります。
建物本体の費用だけでなく、土地、外構、諸費用、そして税金や引っ越し費用まで含めて、すべてを見通した資金計画が必要です。
特に注意したいのは、「建てた後にかかるお金」を見落としがちだということ。
どんなに素敵な家を建てても、ランニングコストが高かったり、将来のメンテナンス費がかさむようでは、暮らしの質を落としてしまいます。
そのため、建築時の初期費用だけでなく、30年後まで見据えた“トータルコスト”を考える家づくりが重要です。
また、資金計画とは単に「いくら借りて、月々いくら返すか」だけを決めることではありません。
それは単なる返済計画にすぎません。
本来の資金計画とは、「35年間、安心して暮らせるために“お金と暮らし”をどう整えるか」を考えること。
未来の家族構成、教育費、車の買い替え、老後の備えまで含めて、「お金」と「時間」の両方にゆとりを持たせるためのシミュレーションが必要です。
クオホームでは、お客様一人ひとりの将来像に合わせた「暮らしの質」を支える家づくりを大切にしています。
その第一歩として、まずは家づくりにかかるお金の全体像を正しく理解し、建ててからお金がかからない家づくり=“後悔しない選択”をしていただきたいと考えています。
家づくりには、実にさまざまなお金がかかります。
たとえば建物本体にかかる工事費だけではなく、別途工事費、諸費用、土地の取得費用、外構工事費、そして税金や引っ越し費用まで、実に多岐にわたります。
これらの費用をすべて含めて「家づくりに必要なお金の全体像」として把握しておくことが重要です。
なぜなら、モデルハウスや広告などで表示される価格には、建物本体の価格しか書かれていないことが多く、「あとから費用がどんどん追加されてしまった…」という声が後を絶たないからです。
「建物価格が◯千万円」と聞くと、その金額だけで家が建つと思いがちですが、実際には総額でその1.2倍〜1.5倍ほどかかることも珍しくありません。
たとえば、建物価格が2,000万円の場合、総費用は2,400〜3,000万円程度になることもあります。
これは決して“オーバー”ではなく、家づくりではごく一般的な現象なのです。
ですから、家づくりの予算を考えるときは、まず「建物価格=家の価格」ではないという前提に立ち、「家づくりにかかるすべてのお金」をトータルで把握することが欠かせません。
それが、資金計画の第一歩になります。
1-2 家づくりにはどんなお金がかかるの?
家づくりには、実にさまざまなお金がかかります。
たとえば建物本体にかかる工事費だけではなく、別途工事費、諸費用、土地の取得費用、外構工事費、そして税金や引っ越し費用まで、実に多岐にわたります。
これらの費用をすべて含めて「家づくりに必要なお金の全体像」として把握しておくことが重要です。
なぜなら、モデルハウスや広告などで表示される価格には、建物本体の価格しか書かれていないことが多く、「あとから費用がどんどん追加されてしまった…」という声が後を絶たないからです。
「建物価格が◯千万円」と聞くと、その金額だけで家が建つと思いがちですが、実際には総額でその1.2倍〜1.5倍ほどかかることも珍しくありません。
たとえば、建物価格が2,000万円の場合、総費用は2,400〜3,000万円程度になることもあります。
これは決して“オーバー”ではなく、家づくりではごく一般的な現象なのです。
ですから、家づくりの予算を考えるときは、まず「建物価格=家の価格」ではないという前提に立ち、「家づくりにかかるすべてのお金」をトータルで把握することが欠かせません。
それが、資金計画の第一歩になります。
1-3 別途工事費って何?いくらくらいかかるもの?
「別途工事費」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
これは、建物本体の工事費とは別にかかる費用で、建物を建てるために必要不可欠な工事なのに、本体価格には含まれていない費用のことを指します。
代表的なものとしては、以下のような項目があります。
・地盤調査・地盤改良工事
・仮設工事(足場、仮設トイレ、仮設電気など)
・給排水工事(敷地内の上下水道の引込や整備)
・雨水排水工事
・電気引込工事
・ガス引込工事(都市ガスエリアの場合)
これらの工事は、家を安全・快適に建てるために必要不可欠なものであり、実質的には「家の一部」とも言える内容です。
しかし多くのハウスメーカーや工務店では、これらの費用を本体価格に含めず、「別途工事費」として契約後に加算するスタイルをとっています。
そのため、建物価格だけを見て契約してしまうと、あとから「こんなに費用が追加されるなんて…」と驚くケースも少なくありません。
別途工事費の金額は、敷地条件や工事内容によって大きく変わりますが、一般的には100万〜200万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
特に注意したいのは、地盤改良工事が発生する場合です。
この費用は地盤調査の結果が出るまで正確にはわかりませんが、改良が必要と判断された場合は、30万〜100万円以上かかることもあります。
クオホームでは、こうした別途工事費もはじめから資金計画に含めてご提示し、「最終的にいくらかかるのか」がわかる、明瞭な見積もりを大切にしています。
価格の見せ方に惑わされず、トータルで安心できる家づくりを選ぶことが、後悔しないポイントです。
1-4 諸費用って何?いくらくらいかかるもの?
「諸費用」とは、建物の本体工事費や別途工事費とは別にかかる、さまざまな費用の総称です。
具体的には、以下のような項目が含まれます。
・住宅ローンに関する費用(事務手数料・保証料・印紙代など)
・火災保険料・地震保険料
・登記費用(登録免許税・司法書士報酬など)
・不動産取得税
・固定資産税(精算分)
・水道加入金(地域によって異なる)
・引っ越し費用や仮住まい費用(建て替えの場合)
・家具・家電の購入費用
これらの費用は現金で支払う必要がある場合も多く、家づくりにおける「見えにくいけれど確実にかかるお金」と言えるでしょう。
諸費用の総額は、建物価格の5〜10%程度が目安です。
たとえば、建物価格が3,000万円の場合は、150万〜300万円ほどかかることになります。
この金額は、ローンの借入額や火災保険の加入条件、建て替えか新築かなどの条件によって大きく変わるため、早めに具体的な見積もりをもらっておくことが大切です。
クオホームでは、こうした諸費用も資金計画の初期段階から丁寧にご説明し、「あとからこんなにかかると思わなかった…」を防ぐサポートを行っています。
家づくりの本当の安心は、こうした細かな費用までしっかり把握することから始まります。
1-5. 無理のない資金計画のためにしておくといいことは?
家づくりは「建てるまでのお金」だけでなく、「建てた後のお金」まで含めて考える必要があります。
将来まで安心して暮らし続けるためには、“無理のない資金計画”を立てることが何より大切です。
そのために、まずやっておきたいのが、「今のお金の流れを把握すること」。
・月々の収入は?
・固定費(家賃、保険、通信費、教育費など)は?
・変動費(食費、レジャー費など)は?
・毎月いくら貯金できているか?
このように「現在の支出構造」を見える化することで、家計の中で無理なく返済できる金額が見えてきます。
また、将来的な支出も視野に入れることが重要です。
たとえば、子どもの教育費・車の買い替え・家族旅行・老後資金など、家を建てた後にも大きな支出は続きます。
これらを考慮せずに返済計画を立ててしまうと、将来どこかで家計が破綻するリスクも生じます。
クオホームでは、住宅ローンにかけられる金額を単に「借りられる額」ではなく、「無理なく払える額」から逆算するという考え方を大切にしています。
そのため、資金計画の初期段階で「ライフプランシミュレーション」を行い、35年間の暮らしを見通した設計をご提案しています。
これは単なるお金の計算ではなく、家族の未来に寄り添うための“暮らしの質”を守る大切な作業です。
「建てたはいいけど、旅行にも行けない」「貯金ができなくて不安」というような暮らしにならないためにも、事前の準備が将来の安心につながります。
1-6. 住宅ローンっていくらくらい借りられるの?
住宅ローンは、多くの人にとって「人生で一番大きな借金」です。
だからこそ、「いくら借りられるか」ではなく「いくらなら無理なく返せるか」を基準に考えることがとても重要です。
一般的に、住宅ローンの借入可能額は、年収に対する返済負担率によって決まります。
たとえば、年収400万円の方であれば、返済負担率30〜35%程度とされ、年間返済額が120〜140万円までに収まる借入額が上限になります。
これを35年返済・金利1.0%程度で試算すると、およそ3,000万〜3,500万円が借入可能な目安となります。
ただし、これはあくまで「借りられる額」の話であり、「返せる額」とは別問題です。
たとえ金融機関が3,500万円貸してくれても、その返済額が生活を圧迫するようであれば、本末転倒です。
さらに、子どもの教育費や車の買い替え、老後資金といった将来の出費も考慮しなければ、「家を買って生活が苦しくなった」という事態にもなりかねません。
クオホームでは、住宅ローンの組み方に関しても、「安心して35年間返し続けられるか?」という視点でご提案しています。
また、ライフプランをもとにした住宅ローンシミュレーションも実施し、毎月の家計に無理が出ないようサポートしています。
借りられる限界まで借りるのではなく、「無理なく返せる額」から逆算して家づくりを考える。
それが、安心で豊かな暮らしを実現するための第一歩です。
1-7. みんないくらくらいの住宅ローンを借りてるの?
「うちはどれくらい借りても大丈夫?」と考える前に、まずは他の人がどれくらい住宅ローンを借りているのかを知っておくのも安心材料の一つです。
国土交通省の「令和4年度 住宅市場動向調査」によると、注文住宅を建てた人の平均借入額は、
全国平均で3,382万円
近畿圏平均で3,491万円
となっています。
また、住宅取得者の年収を見ると、全国平均で約630万円という結果も出ています。
このことから、「年収の5〜6倍程度を借り入れている人が多い」という傾向がわかります。
もちろんこれはあくまで平均値なので、年収や家族構成、将来のライフプランによって適正額は変わります。
しかし、「年収の7倍以上」など過剰な借入は、家計への負担が大きくなる可能性があるため注意が必要です。
クオホームでは、お客様の年収だけでなく、将来の生活スタイルや教育費、老後の資金計画まで見据えた資金計画をご提案しています。
住宅ローンの金額は「他の人がどれくらい借りているか」ではなく、「自分たちの暮らしに合っているか」で判断することが大切です。
1-8. 頭金を用意することでどんなメリットがあるの?
住宅ローンを組む際に、「頭金を入れるべきかどうか」は、多くの人が悩むポイントです。
頭金とは、住宅購入費用のうち、ローンを組まずに自己資金として支払う部分のことです。
たとえば、3,000万円の家を購入する場合、300万円を頭金として用意すれば、ローンの借入額は2,700万円になります。
では、頭金を用意することで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
1. 借入額が少なくなる
借入額が減ることで、毎月の返済額が抑えられ、家計の負担が軽くなります。
2. 総返済額が少なくなる
借入額が少ないということは、当然ながら利息も少なくなります。
結果として、35年間で支払う総額が大きく減ることになります。
3. ローン審査で有利になる
頭金を多く用意できるということは、「計画的に資金を準備できている人」として金融機関から評価され、審査に通りやすくなったり、好条件の金利が提示されたりする可能性があります。
4. 借入上限に近づきすぎずに済む
頭金を入れない場合、借入額が年収の限界に近づいてしまい、今後の支出に余裕が持てなくなるリスクも高まります。
ただし、頭金を無理に準備しすぎて、貯金がゼロになるのは避けましょう。
引っ越し費用や家具・家電の購入費、予期せぬ出費に備えて、手元に100万〜200万円程度の生活予備費を残しておくことも大切です。
クオホームでは、お客様のご状況に応じて、頭金を含めた資金のバランスをご提案しています。
「頭金がいくら必要か」ではなく、「いくら残しておくべきか」も含めて考えることで、より安心できる資金計画が実現します。
1-9. 広告に書かれている「坪単価」って何?
住宅会社の広告やホームページを見ていると、よく目にするのが「坪単価○○万円~」という表記。
この坪単価とは、建物の1坪(約3.3㎡)あたりの建築費を表す単価のことです。
たとえば、「坪単価60万円」と記載があり、延床面積が35坪の家を建てるとすると、
60万円 × 35坪 = 2,100万円が建物の本体工事費の目安になります。
ただし、ここで注意したいのは、この「坪単価」に含まれている範囲が住宅会社によってバラバラという点です。
同じ坪単価でも、
・キッチンやお風呂のグレードは?
・照明・カーテンは含まれている?
・外構工事や付帯工事は?
・設計料や監理料は?
といった要素によって、最終的な総額に大きな違いが出る可能性があります。
つまり、坪単価だけを見て「安い・高い」を判断するのはとても危険ということです。
また、安く見せるために「延床面積を小さく」「設備のグレードを下げる」などの工夫をしている会社もあるため、その中身をしっかり確認することが大切です。
クオホームでは、お客様が誤解をしないよう、坪単価ではなく「総額」でご案内することを基本としています。
実際に住める状態になるまでにいくらかかるのか?をわかりやすく提示し、ご納得いただいたうえで家づくりを進めていきます。
坪単価はあくまで目安。
大切なのは、自分たちの暮らしに必要なものを含めた「最終的な総額」で比較することです。
1-10. 坪単価に差が出るのはなぜ?
同じような住宅でも、なぜこんなに「坪単価」に差があるのか。
これは、家づくりを考える人が最初に疑問に感じるポイントかもしれません。
坪単価に差が出る理由には、いくつかの要因があります。
1. 仕様や設備のグレードの違い
キッチンや浴室、外壁や屋根など、使われる素材や設備のグレードによって、建築費は大きく変わります。
見た目は似ていても、断熱性能や耐久性、保証内容などがまったく異なるケースも。
2. 工事に含まれる範囲が違う
坪単価の中に何が含まれているかは、住宅会社によってバラバラです。
外構工事や付帯工事、照明・カーテン、エアコンなどが別途費用になることもあります。
3. 設計・監理料が含まれているかどうか
設計事務所や工務店では、設計・監理に対する費用が明確に含まれていることがあります。
一方で、大手ハウスメーカーでは営業費や広告費が建物価格に上乗せされている場合もあるため、比較はより慎重に。
4. 建物の形状や延床面積
同じ坪単価でも、総額に影響するのは「延床面積」や「建物の複雑さ」です。
複雑な形状や凹凸の多い間取りになると、施工コストが増えるため坪単価も上がります。
つまり、坪単価は「家の本質的な価値」や「最終的な支払い総額」を正確には示していないということ。
クオホームでは、坪単価ではなく「最終的にかかる全体費用」でご案内することで、「こんなはずじゃなかった」をなくすことを大切にしています。
本当に大事なのは、自分たちの暮らしに合った性能や仕様を、納得できる価格で手に入れることです。
1-11. 注文住宅を建てるためのお金はいつ支払うの?
注文住宅の魅力は、間取りや素材、設備を自分たちで自由に選べること。
しかし、「お金はいつ払うの?」「タイミングごとにいくらくらい必要?」という点が不安な方も多いのではないでしょうか。
注文住宅のお金の支払いは、大きく分けて3〜5回に分かれて発生します。
1. 契約時(請負契約)
まずは住宅会社と工事請負契約を交わした段階で、契約金として総工事費の5%〜10%程度を支払うケースが多いです。
2. 着工時
工事が始まる段階で、総工事費の30〜40%程度を支払います。
この時点では、住宅ローンはまだ実行されていない場合が多く、つなぎ融資や自己資金が必要になることもあります。
3. 上棟時(中間金)
建物の骨組みが完成する「上棟(じょうとう)」のタイミングで、中間金として30%前後を支払います。
4. 竣工・引渡し時
建物が完成し、いよいよ引渡しとなる段階で、残金(20〜30%程度)を支払います。
このタイミングで住宅ローンが実行されることが多く、それまでの支払いをどうつなぐかがポイントになります。
5. 外構工事やオプションなど
建物本体とは別に、外構工事や照明・カーテンなどのオプションがある場合は、それらの支払いが別途発生することもあります。
つまり、家づくりには「まとまったお金が何度かに分けて必要になる」ということをあらかじめ知っておくことが大切です。
クオホームでは、お客様の資金状況に合わせた支払い計画のご提案を行っており、「いつ・いくら必要か」を丁寧にご説明しています。
資金の流れをしっかり把握することが、安心して家づくりを進める第一歩です。
1. 解体工事って何?どのくらいコストがかかるの?
建て替えや古家付き土地の購入を検討している方にとって、避けて通れないのが「解体工事」です。
この工事には一定の費用がかかるため、家づくりの総予算にあらかじめ組み込んでおくことが大切です。
2. 解体工事とは?
解体工事とは、既存の建物を壊して撤去し、更地の状態に戻すための工事のことです。
木造住宅、鉄骨造、RC造(鉄筋コンクリート造)など、構造によって方法や手間が異なり、費用にも大きく影響します。
また、建物だけでなく、基礎の撤去・コンクリートのガラ処理・浄化槽や井戸・植栽の撤去、場合によってはアスベスト処理なども含まれることがあります。
3. 解体工事の費用相場(目安)
以下は一般的な坪単価と、30坪程度の家を解体した場合の費用目安です。
| 構造 | 坪単価(目安) | 30坪の家を解体した場合の目安 |
|---|---|---|
| 木造住宅 | 約3〜5万円/坪 | 約90万〜150万円 |
| 軽量鉄骨造 | 約4〜6万円/坪 | 約120万〜180万円 |
| RC造 | 約6〜8万円/坪 | 約180万〜240万円 |
※地域差・立地条件・重機の搬入可否・土中の埋設物などにより上下します。
4. 解体費用が高くなるケースとは?
以下のような条件では、解体費用が数十万円〜100万円以上増加することもあります。
- 狭小地で重機が入らない場合(手壊し)
- アスベストが使用されている場合(処理費用が高額)
- 地下室や大型基礎、井戸、古い浄化槽などの撤去が必要な場合
- 隣地との距離が近く、養生や人件費が多くかかる場合
5. クオホームの考え方:解体費も含めた「総額予算」で考える
家づくりでは、「建物価格」だけでなく、解体費・外構・諸費用を含めた“本当の総額”で予算を立てることが大切です。
クオホームでは、初期相談の段階から「解体が必要な土地かどうか」「想定される費用」「事前に確認すべき法規制」などを細かくチェックし、想定外の出費が出ないように、丁寧にお金の流れをご説明しています。
また、空き家の登記簿上の所有者確認や、解体前のライフラインの停止手続き(ガス・電気・水道)なども、見落とされがちな大事なポイントです。
6. まとめ
・解体工事は建て替え時や古家付き土地購入時に必須
・木造30坪で約100万〜150万円が相場
・条件によって金額が大きく変動するため、事前調査が重要
・クオホームでは「土地購入前の現地調査」や「解体費用の見積もり調整」もサポート